|
「諏訪」地区利活用案(検討委員会案) |
諏訪地区(旧入遠野製品事業所)の利活用案がまとまりました。
この案をたたき台に、遠野町地域づくり振興協議会の利活用案として
まとめていきたいと考えていますので、
多くの人たちの御意見・御感想をお待ちしております。
目 次
| ●諏訪地区の概要 | ●利活用の基本的な考え方 |
| ●利活用にあたっての問題点と解決策 | ●利活用の利点 |
| ●利活用の内容 | ●効率的な利活用の手法・方法等 |
| ●新たに整備する施設等 | ●利活用の手法例(手段、段階等) |
| ・諏訪地区の概要 |
| 敷地面積 | 7,463平米 | |||
| 既存建物 | 13棟(昭和43年頃建設・築約30年) | |||
| 事務所 |
196.88平米
|
59.66坪
|
1棟
|
|
| 住 宅 |
79.34平米
|
24坪
|
9棟
|
|
|
39.74平米
|
12坪
|
3棟
|
||
| 車 庫 |
51.12平米
|
15.5坪
|
1棟
|
|
| 入遠野地区の国有林(杉、檜)を主とする、562ヘクタールを対象に事業が行われ、その事務所と住宅として 使用された地区。使用されなくなって10数年経過している。 |

| 入遠野製品事業所建物位置図(いわき市遠野町入遠野字諏訪90) |
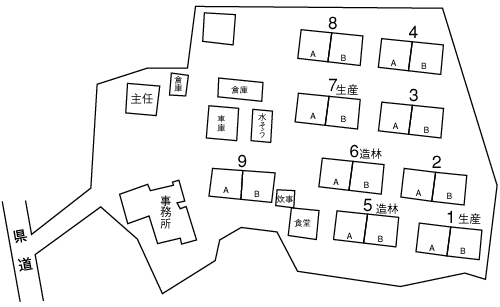 |
| 現況写真 |
 |
 |
 |
 |
|
・利活用の基本的な考え方 |
| 「川の家構想(仮称)」における「諏訪地区」の導入機能を継承し、 「地域情報ターミナルゾーン(遠野をみせる)」として位置づける。 |
| 1 |
遠野町の歴史的資産、伝統を充分活かす。 |
| 2 | 使い捨て文化の見なおしと資源の効率的な利用を考えるモデルとする。 |
| 3 | 隣接する「遠野オートキャンプ場」と利用や管理運営での連携。町内外の宿泊施設との連携も積極的に行なう。 |
| 4 | 内外から広く人材を求め、次世代への伝統の業を継承するシステムを構築する。 |
| 5 | 太陽光、風力等の新エネルギーの利用と雨水や下水の利用モデルと位置づける。 |
| 6 | 利用したい人が誰でも参加できるシステムを構築する。 |
|
・利活用にあたっての問題点と解決策 |
|
1−既存建物の耐久性と安全性、充分な光熱水源と環境に配慮した排水 |
| 建物の利用 | 建築後30年、放置されて約10年経過した、既存木造建物13棟の再利用。 屋根、外壁が破損して、修復困難な建物は、空きスペースを作り出す意味で取り壊す必要がある。 |
| 水の確保 | 当時は、入遠野川から取水し、給水管により各戸、給水していたが、長期間放置されていたため、再利用 のための修復は困難である。 そのため敷地内での井戸掘削と併せ雨水利を検討することが最良と考えられる。 |
|
2−運営母体と運転資金不確定 |
| 運営母体は、近接するキャンプ場の管理を市から委託されている「遠野オートキャンプ場管理運営委員会」 が核となり、地元経済団体、利用者が運営組織を立ち上げる。 |
|
3−恒常的運営のための人材の確保(管理と制作・指導の両面) |
| 現状のキャンプ場スタッフの要請と平行して町内外から、施設を利用・活用したい人(製作と指導の両面ができる人材)を公募する。 |
|
4−周辺環境(周囲の山など)の活用 |
| 北側に隣接する、諏訪神社、周辺の農地を取り込んだ利用も今後の検討課題、駐車場野確保 |
|
・諏訪地区の利活用の利点 |
| 1 |
遠野オートキャンプ場の近くで、利便性と相乗効果が高い。 |
| 2 | 地域振興を図る分野の活力を効率的に集中・統合できる位置にある。 |
| 3 | 優れた伝統的技能・工芸(いわき和紙、野鍛冶、竹・藁・つる細工、桶樽)が伝承されている。。 |
| 4 | 既存建造物の再利用は、時代のニーズに適合している。 |
| 5 | 遠野を象徴する美しい里山の自然景観を活かせる。 |
|
・利活用の内容 |
| (前提条件) さわって、学んで、感激できるミニ博物館(美術館)の役割を持たせる。 誰でも利用できる、楽しい空間 利用者のコミュニケーション、交流の促進 |
|
1−既存建物の利用 |
|
利用内容
|
機 能
|
|
伝統工芸
|
・いわき遠野和紙(上遠野紙)の継承・体験、道具類の保存 |
|
農林業
(山里生活) |
・農作業休憩小屋(機械・道具類の収納を含む) |
|
管理・展示販売
|
・事務室 |
|
フリースペース
|
・貸しアトリエ |
|
2−周辺整備 |
| ・ | 隣接する諏訪神社の環境整備 |
| ・ | 敷地内に、各施設の利活用内容と関連する「ミツマタ」「楮(こうぞ)」「柿」「こんにゃく」等を植採 |
| ・ | 体験農園の整備 |
| ・ | 将来、駐車場スペースの確保等 |
|
・効率的な利活用の手法・方法等 |
| 1 | 週休2日に伴う子供の積極的な受け入れ。 |
| 2 | 学校、子供会、サークルの体験学習の受け入れ。 |
| 3 | 地域の人たちが楽しみに集まってくる工夫。 |
| 4 | 他地区(いわき湯本温泉組合等)との連携、コース化を図る。 |
| 5 | 市内をはじめ首都圏からの利用客を募る。 |
| 6 | 幅広い多数の指導者層の確保を図る。 |
| 7 | 他にまたがる広い呼びかけ。 |
| 8 | キャンプ場と一体化した運営(民間組織による柔軟な運営)、利用者のための制作体験コースの設定。 |
|
・新たに整備する施設 |
| 1 |
施設内道路の整備
|
| 2 | 駐車場の整備 |
| 3 | 建物の整備(外装・内装の一部) |
| 4 | 上水道(飲み水は井戸、中水は雨水等を利用) |
| 5 | 下水道(合併浄化槽) |
| 6 | 電気設備(将来、太陽光、風力利用などを視野に入れて) |
|
・利活用の手法例(手段・段階等) |
|
第1段階−利活用の公表と意見聴取等 |
| 「諏訪地区」の利活用について、町内に広く認知され、利活用案作成・実施に参加してもらうため「諏訪地区」 利活用調査・検討委員会の活用案を地域振興広報紙「広報とおの」等で公表するとともにアンケート調査を行う。 また「遠野まちづくり交流会」等で、広く意見を聞き、利活用案の更なる改善を図る。 |
|
第2段階−イベントの開催 |
| 地域の合意の基、諏訪地区を地元の人はもちろんのこと市内外に広く宣伝するとともに、利活用案をPRし、 計画の参画者を募りため開催する。 |
| 例 | 「(仮称)遠野町蔵出しフリーマーケット」 農家の道具、食べ物、生活用品等まるごと商品として展示・実演・販売する。 場所は、諏訪地区、オートキャンプ場及び町内各地 |
| 農家、各集落、神社、寺院に伝わる「お宝」も紹介する。 | |
| 「そば、うどん屋」など飲食店や青空市も同時に開催する。(アンケート調査を行う) |
|
第3段階−利活用案のビジュアル化とアイデア・使用者募集 |
| イベントと同時に、利活用案をビジュアル化し、広く公開するととに「私ならこう使う」というアイデアを公募す る。 また、諏訪地区の建物の一部を簡便に整備し、一定期間テナントを募集し、今後の進め方の参考とする。 |
|
第4段階- |
|
各段階のステップを踏まえて、遠野地区外を問わず「諏訪地区」本気で利用したい個人、団体を先選考して、
利用者を決定し、利用者が整備を進めながら利用者と地元(オートキャンプ場管理運営委員会等)で管理運営委員会を立ち上
げる。
この際、建物は徐々に整備していくことを心がける、急がない。 |